童話 サンショウじいさん
杉 左近
あまり荒らされていない古い川ならば、どの川にも「川の主」というものがいるものです。砂防の上の深みに住む大ウナギだったら、人の近寄ることもない大柳の根ったの洞(うろ)が、彼のお城になっていることでしょう。山のツツミの主は、ヒシの葉っぱの下の下、深あい泥の底に住む年とった大スッポンかもしれません。
さて、これからお話しようとする「鳥谷川」は、福井県と京都府の境の大きな山にしみこんだ水を、チョロチョロ、チョロチョロと集めて、深い深い谷をつくり、県道の下十数メートルのところを流れて村へ出てくる、谷川なのです。
古い大カエデ、新しく細いカエデ、ツバキ、トチ、ふとくて強いフジ。それらの緑の葉っぱが重なりあって、太陽の光の玉が水の上にこぼれるようすは、下流では見ることのできない美しさです。
川の両がわにもまんなかにも、十人かかっても動かせそうもない大きな岩が、ごろごろしていて、その岩と岩の間を、すきとおるようなきれいな水が、なにかをささやきながら、チルチル、コロコロと流れていきます。
なかでも大きな黒っぽい岩の下が、えぐられたように深くなっていて、青黒い水がゆっくりとうずをまいています。鳥谷川の主「サンショウじいさん」のお城は、その岩の下にあるのです。
私が、その鳥谷川の主に初めて出あったのは、そうですね、八つか九つのころだから、かれこれ七十年にもなりましょう。県境の山で炭を焼いているととさんが忘れて行った、たばこ入れときせるをとどけに行ったときのことです。四キロメートルもあるさびしい坂道を、すたこらすたこらと歩いて行ったのですから、昔の子どもは、歩くことには、なれていたのですね。
県境近くまでくると、さすがにのどがかわいて、水が呑みたくなりました。私は、落ちたら死んでしまいそうな深い谷へ、ツバキやカエデの木につかまりながら、そろりそろりとおりていきました。
半分ほどおりたところで、ひょいと下を見ると、岩の上に、だれかがすわっているのが見えました。びっくりしてあともどりをしようとすると、下からやさしい声がおっかけてきました。「おりておいで、おりておいで。」
そーっとふり向いて見ると、岩の上で手まねきをしているのは、みすぼらしいかっこうをして、ぼつぼつだらけの赤い顔をしたおじいさんです。上がることもできず、おりるのもこわく、ツバキの木にしがみついていると、おじいさんが立ちあがって話しかけました。「こわがることはないよ。ここはすずしくてとても気もちがいいから、おじいさんも休んでいるんだよ。さあ、おいで、おいで。」
その声がとてもやさしい声だったので、安心して、また、そろり、そろりとおりていきました。「おお、よく来た、よく来た。」といって、おじいさんは、私にいろいろとたずねたり、話してくれたりしました。村の人々のくらしのこと、田んぼのこと、川のこと、橋のことなど、なんでもめずらしそうに、「ふーん、そうか。ふーん、そうか。」と、うなずきながら聞いて、そのかわりに、めずらしい谷川の魚のことや、岩の下のカニのことなど、たくさん話してくれました。
そして、私が手ですくって飲んだ水の、おいしかったこと。それはそれは、何にもたとえようのない、ゆめを見るようなおいしさでした。あまりのふしぎさに、私は、おじいさんにたずねました。
「おじいさん、どこから来たの。」
すると、おじいさんは、わらいながら岩の下をゆびさして、「あそこだよ。あの、うずをまいている水の底。」そしてこんどは、まがおになってこう言いました。「このことは、ぜったい誰にも言ってはいけないよ。わしは、この鳥谷川の主なんじゃ。この川を、いつでもやさしくきれいな水が流れるようにまもっているのじゃよ。でもな、人に知られたら、その力がなくなる。」
そう言ったとき、ずっと上の道で、急に犬のほえる声がした。
「ドボーン。」ほんとうにあっというまに、おじいさんは川に飛びこんで、姿を消してしまったのです。
岩の下の、えぐられたような深いところには、もとのように、ゆっくりゆっくりとうずがまいていて、その底に、見たこともない大きなサンショウウオが、さびしそうな目をして、私の顔を見上げていました。
その次にサンショウじいさんに会ったのは、昭和二十八年の、あの十三号台風のすぐあとでした。一夜のうちに、谷も畑も家も橋も、めちゃめちゃに荒らされて、村じゅうが石ころの川原のようになってしまい、黄色くにごった水が、土堤を切って流れていました。
私は、ふと、おじいさんのことが心配になってきました。やくそくを守って誰にも話さず、ただ心の中で、サンショウじいさんという名前をつけて、きれいな川の水を見るたびに思い出していたのです。
(じいさんは、無事に岩の下にいるだろうか。土砂におしつぶされて死んだのではないだろうか。)そう思いながら、私は急いで、鳥谷の坂道を登って行きました。
道をのぼって行くにつれて、道からすかして見る谷川の水は、もとどおりのきれいな水にかえり、めざす大岩は、もとの場所に、でん、とすわっていたので、私は、やれやれと思って、下りていきました。
すこしおりてから岩を見ると、さっき見えなかったおじいさんが、力なくうなだれて、岩の上にすわっていました。私は、なつかしさに思わず、
「おじいさーん、おれだよ。あいに来たよ。」とさけびました。するとどうでしょう。おじいさんが、よろよろっと立ちあがったと思うと、
「ドボーン。」
川の中へすがたを消してしまいました。
「おじいさん、おれだよ。おじいさん、どうしたの。」むちゅうでかけおりた私は、水の底に向かって、何回もさけびました。岩のうらからは、サンショウウオのしっぽだけが見えていて、あわぶくといっしょに、力のない声が聞こえてきました。
「やっぱり、お前だったのか。だけど、わしは、もうだめだ。年をとりすぎて、川の水を、あらしから守る力もなくなってしまった。この川をいつまでも美しく、平和にまもるために、川の主をだれかにゆずって、この岩の下で、静かに一生をおわるだろうよ。」
そう言うと、見えていたしっぽまでも、すうっと岩の下にかくれてしまいました。
「おじいさーん、おじいさーん。死んじゃいけないよお。」
私は、いいおとなになっていることもわすれて、川にさけびつづけた。するともうひと声だけ、はっきりと返ってきた。
「わしは、お前さんが秘密のやくそくを守りつづけてくれたので、人間を最後まで信じることができ、それだけは幸福だったよ。さ、よ、う、なら。」
さ、よ、う、なら、はカエデの葉をサワサワとゆする風の音で、とぎれとぎれに空へまいあがっていった。
その後も、そこを通るたびに、私は、そっと木の葉をすかしてのぞいて見るのですが、ツバキの季節にはツバキの花が、藤のころには藤の花が、ホロホロ、コロコロと、黒い大岩の上にこぼれているばかりです。
(杉 左近詩文集より)

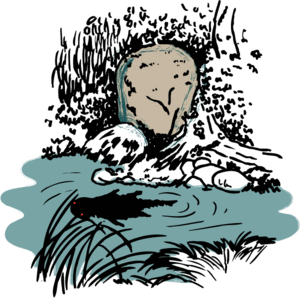

























コメント